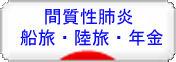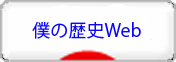だから僕はパリが嫌いだ [若かった頃]
僕が初めてパリに足を踏み入れたのはもう随分も前の話だ。まだTGVもなく、今よりも夜行列車が盛んに走っていたように思う。ユーレイルパスを手にした僕はジュネーブから夜行寝台でパリに向かった。財布をなくしたりして、結構疲れていた。とっぷりと日の暮れたコルナバンの駅から列車に乗り込み、リュックを片がけにして、すでに動き始めた列車の通路をたどって、僕のコンパートメントにたどり着いた。ドアを開けようとしたのだが、カギがかかっていて開かない。何度か切符の番号を見直したりしたが間違いはない。で、コンコンとドアをノックしてみた。この4人部屋の上段のベッドが僕の今夜のねぐらのはずだ。
ヨーロッパの旅行は、列車にかぎる。飛行機は、いかにも海外旅行の外国人で、土地の人々とふれあうことが出来ない。昼間の一日を移動に使わなくてはいけない飛行機とちがって、夜行列車を使えば、寝ているうちに移動ができて効率がいい。ユーレイルパスなら、$8位でクシェット(簡易寝台)が取れて1等だから寝心地も良いのだ。
ややあって、カギがはずされ、ドアがあいた。そこにいたのは大きく胸の開いたネグリジェすがたの、女性であった。一瞬どぎまぎとしたが、しかたがない、僕は切符を見せてこの部屋の上段を使う事を告げた。男性の靴も見えたから、ここを占拠していたのは若いカップルであることはわかった。迷惑そうな様子がありありと見えた。カーテンの陰の男に何か言っていたが、僕のフランス語では内容は理解できなかった。それはそうだろう、1等寝台で二人楽しい旅をしようとしたところに、むさ苦しい東洋人が割り込んできたのだ。
ここは遠慮して、外に出るのが粋な男の振る舞いではないかと思った。だが僕はそんな計らいをするには、疲れすぎていた。上段のベッドによじのぼり、まもなく同室のカップルの事も忘れて眠りに落ちてしまった。目が覚めたときにはもう列車はパリにつき、乗客はだれもいなくて、列車は車庫に向かって動き出そうとしている時であった。あわてて、降りようとして困ったことになっているのに気が付いた。
僕の靴がないのである。いくらベッドの下を捜してみても見つからない。盗む様な代物ではないから、考えられることはあのカップルが報復に僕の靴を捨ててしまったことである。なんと云うことだ。
花の都パリに僕は裸足で降り立つことになってしまった。あのカップルを恨むより、むしろ自分にヨーロッパ的な洗練された行動がとれなかったことの悔後が大きい。やけに重く感じる荷物を持って靴屋を探して歩くのだがなかなか見つからない。ばかばかしさと、恥ずかしさが混じった妙な気持ちだった。どんよりと空はくもり、道ばたには犬の糞が目立った。セーヌ川は汚らしいどぶ川であったし、メトロは改札口を飛び越えるただ乗り客に圧倒されんばかりの喧噪であった。第一印象が後まで尾をひく。あの日以来、何度行っても、パリは僕にとってなじみの悪いヨーロッパのまちなのである。
ヨーロッパの旅行は、列車にかぎる。飛行機は、いかにも海外旅行の外国人で、土地の人々とふれあうことが出来ない。昼間の一日を移動に使わなくてはいけない飛行機とちがって、夜行列車を使えば、寝ているうちに移動ができて効率がいい。ユーレイルパスなら、$8位でクシェット(簡易寝台)が取れて1等だから寝心地も良いのだ。
ややあって、カギがはずされ、ドアがあいた。そこにいたのは大きく胸の開いたネグリジェすがたの、女性であった。一瞬どぎまぎとしたが、しかたがない、僕は切符を見せてこの部屋の上段を使う事を告げた。男性の靴も見えたから、ここを占拠していたのは若いカップルであることはわかった。迷惑そうな様子がありありと見えた。カーテンの陰の男に何か言っていたが、僕のフランス語では内容は理解できなかった。それはそうだろう、1等寝台で二人楽しい旅をしようとしたところに、むさ苦しい東洋人が割り込んできたのだ。
ここは遠慮して、外に出るのが粋な男の振る舞いではないかと思った。だが僕はそんな計らいをするには、疲れすぎていた。上段のベッドによじのぼり、まもなく同室のカップルの事も忘れて眠りに落ちてしまった。目が覚めたときにはもう列車はパリにつき、乗客はだれもいなくて、列車は車庫に向かって動き出そうとしている時であった。あわてて、降りようとして困ったことになっているのに気が付いた。
僕の靴がないのである。いくらベッドの下を捜してみても見つからない。盗む様な代物ではないから、考えられることはあのカップルが報復に僕の靴を捨ててしまったことである。なんと云うことだ。
花の都パリに僕は裸足で降り立つことになってしまった。あのカップルを恨むより、むしろ自分にヨーロッパ的な洗練された行動がとれなかったことの悔後が大きい。やけに重く感じる荷物を持って靴屋を探して歩くのだがなかなか見つからない。ばかばかしさと、恥ずかしさが混じった妙な気持ちだった。どんよりと空はくもり、道ばたには犬の糞が目立った。セーヌ川は汚らしいどぶ川であったし、メトロは改札口を飛び越えるただ乗り客に圧倒されんばかりの喧噪であった。第一印象が後まで尾をひく。あの日以来、何度行っても、パリは僕にとってなじみの悪いヨーロッパのまちなのである。
なぜフォークソングだったのか [若かった頃]
最近はナツメロとしてフォークソングがとり上げられるようになったようだ。「神田川」とか「この広い野原いっぱい」など出てくるが、僕に言わせればこんなものはフォークでもなんでもない。岡林信康とか高田渡なども元祖として言われるようだが、確かにフォーク色は濃くなるがこれでもない。僕がまぎれもないフォークソングだと思うのは、Peat Seegerの「If I had a hammer」だろう。PPMが歌っていた。
いつの世にも歌はあった。橋幸雄「いたこ笠」とか坂本九「しあわせなら手をたたこう」高倉健「網走番外地」が流行っていた。多くの人々はこういった流行を取り入れ、歌を人生のよりどころとしていた。レコード会社は、大衆の気分を取り入れ、歌手に歌わせてていた。しかし、それはどこか遠くの世界での流行で、自分達の世界ではないと感じている集団がいた。それは学生たちだった。
今は誰でも大学に行く時代だから、学生は一般大衆の一部でしかない。しかし、当時の大学進学率は20%程度で、家業を継ぐか、近隣の工場に勤めるかが、一般的な生き方だった。勉強ができるとかできないとかの前に、生き方は決まっていたのだ。
もう少し前の世代なら、田舎から大学に行くなどと言うのは、例外中の例外で、学生は完全なエリートだった。この時代には、「学生さん」という言葉はまだ残っていたが、進学率が20%にもなると、もはや学生は特別な存在ではなくなってきた。エリートから一般大衆への過渡期に遭遇したのが団塊世代の学生達なのである。
エリートではないくせに、一般大衆としての自分が受け止められない。俺達の歌がない。そう感じていた部分が大きかった。レコード会社が提供してくれる歌は、どれもこれも自分たちの感性に合わなかったのだ。政治的にも、学生は孤立していた。
「なんで、アメリカが遠いベトナムにまで軍隊を送り込むのだーーおかしいじゃないか」「なんで中国大陸を無視して台湾を唯一の中国政府とするのだーーおかしいじゃないか」「なんで汚職ばかりを繰り返す自民党だけが議員になるのかーーおかしいじゃないか」。
一般の人たちはこういったことに無関心で、ひたすらオリンピックを楽しんでいるかに思えた。
こうした学生達の思いを受け止める歌が欲しかった。そんな時に現れたのが、フォークソングであり、僕にとっても、PPMとの出会いは感激的なものであった。今までとは質のちがうメロディーも美しかったし、マリーの歌声は澄み渡っていた。
If I had a hammer, I'd hammer in the morning
I'd hammer in the evening, All over this land
I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning,
I'd hammer out love between my brothers and my sisters, All over this land.
「ハンマー持ったら」の意味は、「何でもぶち壊してしまえ」ではないし、大工道具でもない。アメリカ映画でよく出てくる裁判官の木槌だ。もしも僕がハンマーを手にしたら、朝から晩まで、判決出しまくるぞ。あいつら、政治家がやってることは、全部違法だ。こう歌い上げるのだ。興業師やレコード会社におもねったりせず、ギター一本で歌えると言う事が、のめりこみに拍車をかけた。
あちこちの大学でギターをかき鳴らす学生がでてきた。やがて岡林、小室、高田といった音楽的素養のある学生達が日本語で歌を作り出し、フォークソングが、日本で受け入れられやすい形で広まっていった。それは、なかなか素晴らしいものであり、音楽全体に大きな改革をもたらすものだった。しかし、同時に内面への志向を高め日本的な変形が始まった。結果的には、レコード業界にも取り込まれて、甘ったるい青春メロディーがフォークとしてもてはやされるようになっていったのである。
楽器はだれでもうまく弾けるものではない。あきらめて、放り出す奴もいた。僕も、友達にもらったギターを弾いてみんなで歌ったりしたが、もちろん、人に聴かすレベルのものではなかった。今、歌も久しく歌っていない。間質性肺炎で息が短いし、歌おうとしたら、咳込んでどうにもならなくなる。
いつの世にも歌はあった。橋幸雄「いたこ笠」とか坂本九「しあわせなら手をたたこう」高倉健「網走番外地」が流行っていた。多くの人々はこういった流行を取り入れ、歌を人生のよりどころとしていた。レコード会社は、大衆の気分を取り入れ、歌手に歌わせてていた。しかし、それはどこか遠くの世界での流行で、自分達の世界ではないと感じている集団がいた。それは学生たちだった。
今は誰でも大学に行く時代だから、学生は一般大衆の一部でしかない。しかし、当時の大学進学率は20%程度で、家業を継ぐか、近隣の工場に勤めるかが、一般的な生き方だった。勉強ができるとかできないとかの前に、生き方は決まっていたのだ。
もう少し前の世代なら、田舎から大学に行くなどと言うのは、例外中の例外で、学生は完全なエリートだった。この時代には、「学生さん」という言葉はまだ残っていたが、進学率が20%にもなると、もはや学生は特別な存在ではなくなってきた。エリートから一般大衆への過渡期に遭遇したのが団塊世代の学生達なのである。
エリートではないくせに、一般大衆としての自分が受け止められない。俺達の歌がない。そう感じていた部分が大きかった。レコード会社が提供してくれる歌は、どれもこれも自分たちの感性に合わなかったのだ。政治的にも、学生は孤立していた。
「なんで、アメリカが遠いベトナムにまで軍隊を送り込むのだーーおかしいじゃないか」「なんで中国大陸を無視して台湾を唯一の中国政府とするのだーーおかしいじゃないか」「なんで汚職ばかりを繰り返す自民党だけが議員になるのかーーおかしいじゃないか」。
一般の人たちはこういったことに無関心で、ひたすらオリンピックを楽しんでいるかに思えた。
こうした学生達の思いを受け止める歌が欲しかった。そんな時に現れたのが、フォークソングであり、僕にとっても、PPMとの出会いは感激的なものであった。今までとは質のちがうメロディーも美しかったし、マリーの歌声は澄み渡っていた。
If I had a hammer, I'd hammer in the morning
I'd hammer in the evening, All over this land
I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning,
I'd hammer out love between my brothers and my sisters, All over this land.
「ハンマー持ったら」の意味は、「何でもぶち壊してしまえ」ではないし、大工道具でもない。アメリカ映画でよく出てくる裁判官の木槌だ。もしも僕がハンマーを手にしたら、朝から晩まで、判決出しまくるぞ。あいつら、政治家がやってることは、全部違法だ。こう歌い上げるのだ。興業師やレコード会社におもねったりせず、ギター一本で歌えると言う事が、のめりこみに拍車をかけた。
あちこちの大学でギターをかき鳴らす学生がでてきた。やがて岡林、小室、高田といった音楽的素養のある学生達が日本語で歌を作り出し、フォークソングが、日本で受け入れられやすい形で広まっていった。それは、なかなか素晴らしいものであり、音楽全体に大きな改革をもたらすものだった。しかし、同時に内面への志向を高め日本的な変形が始まった。結果的には、レコード業界にも取り込まれて、甘ったるい青春メロディーがフォークとしてもてはやされるようになっていったのである。
楽器はだれでもうまく弾けるものではない。あきらめて、放り出す奴もいた。僕も、友達にもらったギターを弾いてみんなで歌ったりしたが、もちろん、人に聴かすレベルのものではなかった。今、歌も久しく歌っていない。間質性肺炎で息が短いし、歌おうとしたら、咳込んでどうにもならなくなる。
学生運動の時代 [若かった頃]
今の大学と1970年頃の大学では、まったく雰囲気が異なる。当時は学生運動が爆発的に盛り上がり、我々団塊世代は全共闘世代などと言われることが多い。なぜ学生運動が盛んとなり、そしてまた急激に廃れたのかについて解明した論評は見当たらない。単なる回顧として風説をそのまま書いたり、自分を正当化したりする本が多いし、学生時代の言説と現在の自分の矛盾を語りたがらない人も多い。
戦後、日本国憲法の時代になって、一番大きく変わったのは教育である。上下なく、なんでも合議して、民主的に決めることが浸透しようとしていた。世の中ではまだ戦前の慣習がはびこっていたが、学校には民主主義がいち早く取り入れられた。小中学校でも校長ではなく職員会議が最高決定機関だった。教師は生徒に命令することを止め、子ども達は学級会で議長や書記を決めて民主的な手続きでものごとを決めることを学んだ。
大学自治が唱えられ、大学は全く独自の運営を行い、文部省は単なるお世話官庁であることを自認していた。大学の内部も民主的な運営に転換した。1950年に発行された父の学位記を見たら、授与者は学長ではなく教授会だった。各大学に学生自治会が結成され、学生自治会と教授会の協議が重視されるようになっていた。
しかし、日本国憲法が公布された直後から「逆コース」が始まっていた。自衛隊が発足し、勤務評定で教師が校長の配下に置かれ、大学も予算を通じて文部省の支配を受け入れるようになっていったのである。米軍による日本占領が終わったあとも米軍基地が居座り続けるのはおかしい。世の中では、それも仕方ないということで自民党政権が続いたのだが、大学内では安保条約反対が圧倒的に多かった。大学は反政府運動の出撃基地になった。
大学は、理屈で物事を考え、因習の支配が大きかった一般世間と乖離した世界だったのである。大学進学率が10%以下で、殆どの人が大学などには行かなかった時代には、大学が別世界であることも平然と受け入れられていた。若者の10%だけが別の考えを持ったとしても大勢に影響もなかったからである。大学は別の文化を持った特別な場所と認められていたのである。
60年代の高度経済成長は進学率の急激な増加を生み出した。親の農業や商売を受け継いで行くことが一番安定した生活をもたらす時代が終わり、誰でも勉強ができれば大学を目指すという時代が始まったのである。大学進学率は10%を超え、さらに上昇していた。僕が入学した1966年には12%、1975年には28%になった。学生はエリートと呼ぶには多すぎ、一般大衆と考えるには少ない中途半端な存在になった。
地方の高校から都会のメジャーな大学に進学する学生が一番多かったのはこの時代だろう。今は、地方出身者が減ってしまい、一流大学への進学は、都会の有名高校に限られているという。
多くの学生が大学に入ってカルチャーショックを覚えた。確かに世間一般とは別世界なのだ。世間一般は因習に支配されていることに気がつく。大学は理屈どおりのことが当たり前の世界だった。理屈で考えれば共産党の主張が正しい。当時共産党の議席は5人くらいで、世の中でみれば政党支持率は微々たるものだった。それが学内では80%以上の圧倒的な支持率を得ていた大学もあっただろう。学生自治会はきっちりと選挙で役員を決めており、自治会の役員も民主的に選ばれていた。当然、学生自治会は共産党系の人たちが主導していた。
しかし、大学生は大きな不安に取り付かれていた。自分達はもはやエリートではない。象牙の塔は金の力でどんどん蝕まれているように見えた。科研費などといった研究費予算枠が始まり、大学の先生達は文部省に一本釣りされるようになって行った。ベトナム戦争が起こり、大国が罪ないベトナムの人々を苦しめ、日本政府はそれに加担している。学生達は、街頭に出てベトナム反戦を叫び上げた。このままでは埋もれてしまう、世の中を正すことなしに自分達の人生は成り立たない。そういった思いに駆り立てられたのである。鬱憤晴らしにはなったが、無力感が漂っていたことも事実だ。
ベトナム反戦運動を通して過激な行動を主張するグループも現れてきた。こういった過激派は、60年頃からいろいろ活動はしていたのだが、一般の学生とは縁がなかった。学生自治会の役員に立候補したりしていたが、もちろん支持が得られることはなかった。そこで彼らが思いついたのは、「全学共闘会議」「全学闘争委員会」を名乗り、まどろっこしい自治会の議論を飛び越えて行動を起こすことだった。教室をバリケードで封鎖して無理やり学生をストライキに引き込むことをやり出した。
これは大学自治・学生自治を内部から破壊する行為であり、大きな反発を受けた。しかし、大学自治はすでに侵食を受けていたし、このままでは、窒息させられるといった不安な雰囲気は絶えずあったのである。若い教員を排除して教授だけが権力を持つ教授会自治に対する批判も強かった。今から思えば全く自治が無いよりは、はるかにましだ。今まで何の考えもなかった人にとっては、考える機会となったことも事実だ。急に目覚めて全共闘活動家になった人もいる。
以前から過激派は警察との暴力的衝突を繰り返していたが、全共闘の発足で、暴力を学生にも向けるようになった。警察との衝突には負けるのだが学内での暴力は容易に効果があげられた。あちこちで学生自治会の役員を袋叩きにして「全共闘」が勝手にストライキを宣言するようなことが続いた。こういった暴力は一方的なもので、「内ゲバ」などとひとくくりにされるべきものではないのだが、そのように報道され、今も通用しているようだ。話題性・事件性という意味でマスコミが暴力的学生運動ばかりを取り上げたので、学生運動=全共闘といった図式がいつの間にか定着していった。それが政府の意図だったかもしれない。全共闘が掲げた「大学解体」は、ある意味で政府にも都合が良かったのである。
実際には学生自治会を中心とした暴力的でない学生運動も多くあったのだが、こういった運動はマスコミには黙殺された。5000人が集まった集会はニュースに載らず、200人が警察とぶつかった騒動だけが報道された。そうするうちに、学生の中にも過激であることが根源的であるかの思考が広まり、全共闘派が多数になったことはないのだが、ある程度全共闘を容認するような雰囲気が生まれた。クラス活動家だった僕は、分裂・対立を起こさないよう意識的に党派に属することを避けていたのだが、自治会の書記長に選ばれていた。しかし、自治会室は赤軍派に占拠されて、学生大会は流会し、次の執行部を選出できないまま学部を卒業してしまった。この時点で学生自治会は崩壊した。後輩達はバラバラになっており、全員加盟制自治会を運営する意欲を失っていたのだ。
全共闘は派閥に分かれ、行動の先鋭化を競うようになっていった。学生自治会を否定し、異なる意見を集約するのではなく、自己の主張を押し通すことが出発点だから分裂は避けられない。暴力は強い意思の自然な表れとする考え方だから派閥間の抗争も暴力的となり内ゲバが始まった。まじめな友人がどんどん過激な方向に陥って行くのに心を痛めた。
暴力への拝跪が蔓延して行った。根底には百の議論より1つの行動が結果を生み出すといった理性への失望があった。事実、選挙では相手にされなかった学生自治の主導権がゲバ棒1つで吹き飛んだのだ。しかし、暴力で学内を支配して天下を取っても社会の変革とは程遠い。「大学内のお山の大将」だとか、「ちょこっと警察と衝突してみせるお遊び」だとかの批判が一番堪えただろう。彼らは、命がけで本気で革命をやるのが自分の責任の取り方だと追い込まれることになっていった。
人間は自分の命を捨てるつもりになったとき、他人の命も、他の人の暮らしも小さく見えてしまう。過激派はますます過激となり、分裂し互いに殺しあう悲劇を生み、結局は自滅して行った。
大学内が全共闘に暴力的に支配されることになり、一般の学生の多くは、学内のごたごたに嫌気をさして、アルバイトや旅行に日を過ごすことになった。授業もなく試験もなく、そのまま卒業できるのは得だと思っている人もいた。一時は全共闘に共感を覚えた学生も運動からは離脱していった。同時に、自治会を中心とした非暴力の学生運動も衰退して行くことになった。70年以降の学生は、「無関心」か「全共闘」かの二者択一を迫られ、「無関心」にならざるを得なかったのたと思う。なぜ全共闘に共感を覚えたか、なぜ脱落したか、なぜ暴力を容認したかについて、明確に答えられる人は少ないだろう。雰囲気に踊らされた自分の浅はかさを暴露してしまうだけだからだ。
全共闘運動の結果、大学にも傷が残り、ますます自主性を失った。学問の府としての誇りを失い世の中の役に立つことだけを考えるようになった。教授会の権限はなくなり、学長は文科省の意向には逆らえず、研究資金獲得のためにはなんでもする。それが当たり前のようにようになり、今ではほとんどの大学で学生自治会は機能していない。大学生はまぎれもない一般大衆であり、大学は18歳以降の居場所に過ぎない。学生も多大な授業料を卒業後の就職で取り戻すことに必死だ。学生は、完全に沈黙させられているのに近い
学生運動の盛り上がりは、民主主義が日本に導入されて、確立されたかに見えた大学の自治が壊れていく過程で現れた過渡現象だったのである。民主主義に敵対してしまう全共闘の発想自体が思想的屈服だった。一見盛り上がりと見えたのも崩壊の過程で見られたあだ花に過ぎない。だから膨大なエネルギーを費やしたが、何らかの成果が残せるといった筋合いものではあり得なかった。戦後一貫して「逆コース」は続き、アベ政権に至っている。日本人はいつか、徹底的に追い詰められた時に初めて立ち上がるのだろうとは思う。
戦後、日本国憲法の時代になって、一番大きく変わったのは教育である。上下なく、なんでも合議して、民主的に決めることが浸透しようとしていた。世の中ではまだ戦前の慣習がはびこっていたが、学校には民主主義がいち早く取り入れられた。小中学校でも校長ではなく職員会議が最高決定機関だった。教師は生徒に命令することを止め、子ども達は学級会で議長や書記を決めて民主的な手続きでものごとを決めることを学んだ。
大学自治が唱えられ、大学は全く独自の運営を行い、文部省は単なるお世話官庁であることを自認していた。大学の内部も民主的な運営に転換した。1950年に発行された父の学位記を見たら、授与者は学長ではなく教授会だった。各大学に学生自治会が結成され、学生自治会と教授会の協議が重視されるようになっていた。
しかし、日本国憲法が公布された直後から「逆コース」が始まっていた。自衛隊が発足し、勤務評定で教師が校長の配下に置かれ、大学も予算を通じて文部省の支配を受け入れるようになっていったのである。米軍による日本占領が終わったあとも米軍基地が居座り続けるのはおかしい。世の中では、それも仕方ないということで自民党政権が続いたのだが、大学内では安保条約反対が圧倒的に多かった。大学は反政府運動の出撃基地になった。
大学は、理屈で物事を考え、因習の支配が大きかった一般世間と乖離した世界だったのである。大学進学率が10%以下で、殆どの人が大学などには行かなかった時代には、大学が別世界であることも平然と受け入れられていた。若者の10%だけが別の考えを持ったとしても大勢に影響もなかったからである。大学は別の文化を持った特別な場所と認められていたのである。
60年代の高度経済成長は進学率の急激な増加を生み出した。親の農業や商売を受け継いで行くことが一番安定した生活をもたらす時代が終わり、誰でも勉強ができれば大学を目指すという時代が始まったのである。大学進学率は10%を超え、さらに上昇していた。僕が入学した1966年には12%、1975年には28%になった。学生はエリートと呼ぶには多すぎ、一般大衆と考えるには少ない中途半端な存在になった。
地方の高校から都会のメジャーな大学に進学する学生が一番多かったのはこの時代だろう。今は、地方出身者が減ってしまい、一流大学への進学は、都会の有名高校に限られているという。
多くの学生が大学に入ってカルチャーショックを覚えた。確かに世間一般とは別世界なのだ。世間一般は因習に支配されていることに気がつく。大学は理屈どおりのことが当たり前の世界だった。理屈で考えれば共産党の主張が正しい。当時共産党の議席は5人くらいで、世の中でみれば政党支持率は微々たるものだった。それが学内では80%以上の圧倒的な支持率を得ていた大学もあっただろう。学生自治会はきっちりと選挙で役員を決めており、自治会の役員も民主的に選ばれていた。当然、学生自治会は共産党系の人たちが主導していた。
しかし、大学生は大きな不安に取り付かれていた。自分達はもはやエリートではない。象牙の塔は金の力でどんどん蝕まれているように見えた。科研費などといった研究費予算枠が始まり、大学の先生達は文部省に一本釣りされるようになって行った。ベトナム戦争が起こり、大国が罪ないベトナムの人々を苦しめ、日本政府はそれに加担している。学生達は、街頭に出てベトナム反戦を叫び上げた。このままでは埋もれてしまう、世の中を正すことなしに自分達の人生は成り立たない。そういった思いに駆り立てられたのである。鬱憤晴らしにはなったが、無力感が漂っていたことも事実だ。
ベトナム反戦運動を通して過激な行動を主張するグループも現れてきた。こういった過激派は、60年頃からいろいろ活動はしていたのだが、一般の学生とは縁がなかった。学生自治会の役員に立候補したりしていたが、もちろん支持が得られることはなかった。そこで彼らが思いついたのは、「全学共闘会議」「全学闘争委員会」を名乗り、まどろっこしい自治会の議論を飛び越えて行動を起こすことだった。教室をバリケードで封鎖して無理やり学生をストライキに引き込むことをやり出した。
これは大学自治・学生自治を内部から破壊する行為であり、大きな反発を受けた。しかし、大学自治はすでに侵食を受けていたし、このままでは、窒息させられるといった不安な雰囲気は絶えずあったのである。若い教員を排除して教授だけが権力を持つ教授会自治に対する批判も強かった。今から思えば全く自治が無いよりは、はるかにましだ。今まで何の考えもなかった人にとっては、考える機会となったことも事実だ。急に目覚めて全共闘活動家になった人もいる。
以前から過激派は警察との暴力的衝突を繰り返していたが、全共闘の発足で、暴力を学生にも向けるようになった。警察との衝突には負けるのだが学内での暴力は容易に効果があげられた。あちこちで学生自治会の役員を袋叩きにして「全共闘」が勝手にストライキを宣言するようなことが続いた。こういった暴力は一方的なもので、「内ゲバ」などとひとくくりにされるべきものではないのだが、そのように報道され、今も通用しているようだ。話題性・事件性という意味でマスコミが暴力的学生運動ばかりを取り上げたので、学生運動=全共闘といった図式がいつの間にか定着していった。それが政府の意図だったかもしれない。全共闘が掲げた「大学解体」は、ある意味で政府にも都合が良かったのである。
実際には学生自治会を中心とした暴力的でない学生運動も多くあったのだが、こういった運動はマスコミには黙殺された。5000人が集まった集会はニュースに載らず、200人が警察とぶつかった騒動だけが報道された。そうするうちに、学生の中にも過激であることが根源的であるかの思考が広まり、全共闘派が多数になったことはないのだが、ある程度全共闘を容認するような雰囲気が生まれた。クラス活動家だった僕は、分裂・対立を起こさないよう意識的に党派に属することを避けていたのだが、自治会の書記長に選ばれていた。しかし、自治会室は赤軍派に占拠されて、学生大会は流会し、次の執行部を選出できないまま学部を卒業してしまった。この時点で学生自治会は崩壊した。後輩達はバラバラになっており、全員加盟制自治会を運営する意欲を失っていたのだ。
全共闘は派閥に分かれ、行動の先鋭化を競うようになっていった。学生自治会を否定し、異なる意見を集約するのではなく、自己の主張を押し通すことが出発点だから分裂は避けられない。暴力は強い意思の自然な表れとする考え方だから派閥間の抗争も暴力的となり内ゲバが始まった。まじめな友人がどんどん過激な方向に陥って行くのに心を痛めた。
暴力への拝跪が蔓延して行った。根底には百の議論より1つの行動が結果を生み出すといった理性への失望があった。事実、選挙では相手にされなかった学生自治の主導権がゲバ棒1つで吹き飛んだのだ。しかし、暴力で学内を支配して天下を取っても社会の変革とは程遠い。「大学内のお山の大将」だとか、「ちょこっと警察と衝突してみせるお遊び」だとかの批判が一番堪えただろう。彼らは、命がけで本気で革命をやるのが自分の責任の取り方だと追い込まれることになっていった。
人間は自分の命を捨てるつもりになったとき、他人の命も、他の人の暮らしも小さく見えてしまう。過激派はますます過激となり、分裂し互いに殺しあう悲劇を生み、結局は自滅して行った。
大学内が全共闘に暴力的に支配されることになり、一般の学生の多くは、学内のごたごたに嫌気をさして、アルバイトや旅行に日を過ごすことになった。授業もなく試験もなく、そのまま卒業できるのは得だと思っている人もいた。一時は全共闘に共感を覚えた学生も運動からは離脱していった。同時に、自治会を中心とした非暴力の学生運動も衰退して行くことになった。70年以降の学生は、「無関心」か「全共闘」かの二者択一を迫られ、「無関心」にならざるを得なかったのたと思う。なぜ全共闘に共感を覚えたか、なぜ脱落したか、なぜ暴力を容認したかについて、明確に答えられる人は少ないだろう。雰囲気に踊らされた自分の浅はかさを暴露してしまうだけだからだ。
全共闘運動の結果、大学にも傷が残り、ますます自主性を失った。学問の府としての誇りを失い世の中の役に立つことだけを考えるようになった。教授会の権限はなくなり、学長は文科省の意向には逆らえず、研究資金獲得のためにはなんでもする。それが当たり前のようにようになり、今ではほとんどの大学で学生自治会は機能していない。大学生はまぎれもない一般大衆であり、大学は18歳以降の居場所に過ぎない。学生も多大な授業料を卒業後の就職で取り戻すことに必死だ。学生は、完全に沈黙させられているのに近い
学生運動の盛り上がりは、民主主義が日本に導入されて、確立されたかに見えた大学の自治が壊れていく過程で現れた過渡現象だったのである。民主主義に敵対してしまう全共闘の発想自体が思想的屈服だった。一見盛り上がりと見えたのも崩壊の過程で見られたあだ花に過ぎない。だから膨大なエネルギーを費やしたが、何らかの成果が残せるといった筋合いものではあり得なかった。戦後一貫して「逆コース」は続き、アベ政権に至っている。日本人はいつか、徹底的に追い詰められた時に初めて立ち上がるのだろうとは思う。
僕の一番古い記憶 [若かった頃]
ロマンロランの「ジャン・クリストフ」は生まれて来る時の記憶から始まっているが、これは絶対ウソだろう。誰も1歳の時の記憶は持ち合わせていない。僕は1歳のときに「ジフテリア禍事件」に遭遇して人生最大の危機に瀕したはずなのだが、その記憶は全くない。
人間の記憶は大体3歳ころから始まると言われているが、確かに僕の一番古い記憶は3歳の時のことだ。父が若狭湾にある町の病院に赴任して見知らぬ町での生活が始まった。1950年当時は、まだ戦後のどさくさが終わっていない。極端な住宅不足で、おいそれと住む家が見つからない。住む家を見つけるのが大変だったらしい。もちろんこれは、あとで聞いた話だ。
やっと見つけた家は、いわゆる「2戸1」で、一軒の家を半分に切って、玄関を二つ付けた構造のものだ。こういった借家が3軒、まんなかの井戸のある空き地の周りに配置されていた。この井戸は、夏にスイカを吊り下げて冷やすような事はあったが、日常的には使われておらず、代わりに水道の蛇口が1つあった。6軒の家で使う共同水道だ。お母さん達は、ここで交代で洗濯をしたり、米を研いだりして、毎日が近所付き合いだった。まさに「井戸端会議」の場だ。もちろん、風呂はなく、歩いて10分くらいの銭湯に通っていた。
僕は、引っ越した家から、おずおずと外に踏み出した。不安と期待で胸がいっぱいだったに違いない。広場では何人かの子ども達が集まって遊んでいた。遊びの仲間に入れてもらい、ここで年齢を聞かれた。指を3本出して「3つ」と答えたのを鮮明に覚えている。だから、僕の一番古い記憶が3歳であることは間違いがない。
「ゆきちゃん」のお父さんは、国鉄の保線係というか線路工夫、「まあちゃん」のお父さんは大工さん、「たけちゃん」の家は、数軒離れたたところにある駄菓子屋さんだった。リーダーは「かいちゃちゃん」で、2つくらい年上の、医院の子だった。僕は、3年後にはまた引越ししてしまったから、この子たちとはその後の連絡がない。みんな元気のよいワンパク少年で、魚をすくったり、トンボを追いかけたりの楽しい毎日だった。格差が少なく誰もが庶民だった時代だ。
他の子はともかく、この「かいちゃちゃん」の本名が何だったのかがずっと謎だった。母が死ぬ前に教えてくれて「カズヒサ」だったことがわかった。呼び名とは妙なものだ。僕は「ぼやちゃん」と呼ばれていた。母親が「坊や」と言ったのが、名前と解釈されたらしい。「まあちゃん」のお父さんは、遠くで仕事をしているということだったが、実はコソ泥をしてしまって、刑務所にいたことも、60年経ってから知った。
ここでの、大きな事件は、13号台風だった。2015年にも常総市で洪水の被害があり、大きく報道されったが、結局死者はでなかった。当時は毎年、台風で死者が出るのが当たり前だった。1953年の台風13号は、死者393名行方不明85名という記録になっているから、熊本地震など昨今の自然災害の比ではない。
近くの与保呂川があふれて、家の周り一面も水が流れる状態になった。事態の深刻さを知らない僕は折り紙で舟を作って流したりしてご機嫌だった。ところが、水が玄関にも流れ込み、僕の下駄が浮き出した。このとき初めて恐怖を感じたのだろう。とたんに僕は泣き出してしまった。地についてるはずの下駄が浮きだしたことが恐怖の引き金になったのだ。プカプカ浮かぶ下駄を覚えている。消防団の人達が、僕を抱えて濁流を渡ってくれて、一段高い線路伝いに山際の神社まで避難した。
翌朝は晴れて、いい天気だったのだが、あたり一面は泥で埋まっていた。長靴を履いた僕も家に帰ろうとしたのだが、泥に長靴を取られて、すっぽり抜けた足で泥の中に踏み込んでしまった。これが、「しまった」と思った瞬間の最も古い記憶だ。その後も、「しまった」と思う度にこのときのことを思い出す。
これだけ鮮明な記憶が、確かに半世紀以上も昔のことであるとは、実に不思議な気がする。ときどき「あなたの一番古い記憶は何歳の時ですか?」と聞いてみるのだが、明確に答える人は少ない。
人間の記憶は大体3歳ころから始まると言われているが、確かに僕の一番古い記憶は3歳の時のことだ。父が若狭湾にある町の病院に赴任して見知らぬ町での生活が始まった。1950年当時は、まだ戦後のどさくさが終わっていない。極端な住宅不足で、おいそれと住む家が見つからない。住む家を見つけるのが大変だったらしい。もちろんこれは、あとで聞いた話だ。
やっと見つけた家は、いわゆる「2戸1」で、一軒の家を半分に切って、玄関を二つ付けた構造のものだ。こういった借家が3軒、まんなかの井戸のある空き地の周りに配置されていた。この井戸は、夏にスイカを吊り下げて冷やすような事はあったが、日常的には使われておらず、代わりに水道の蛇口が1つあった。6軒の家で使う共同水道だ。お母さん達は、ここで交代で洗濯をしたり、米を研いだりして、毎日が近所付き合いだった。まさに「井戸端会議」の場だ。もちろん、風呂はなく、歩いて10分くらいの銭湯に通っていた。
僕は、引っ越した家から、おずおずと外に踏み出した。不安と期待で胸がいっぱいだったに違いない。広場では何人かの子ども達が集まって遊んでいた。遊びの仲間に入れてもらい、ここで年齢を聞かれた。指を3本出して「3つ」と答えたのを鮮明に覚えている。だから、僕の一番古い記憶が3歳であることは間違いがない。
「ゆきちゃん」のお父さんは、国鉄の保線係というか線路工夫、「まあちゃん」のお父さんは大工さん、「たけちゃん」の家は、数軒離れたたところにある駄菓子屋さんだった。リーダーは「かいちゃちゃん」で、2つくらい年上の、医院の子だった。僕は、3年後にはまた引越ししてしまったから、この子たちとはその後の連絡がない。みんな元気のよいワンパク少年で、魚をすくったり、トンボを追いかけたりの楽しい毎日だった。格差が少なく誰もが庶民だった時代だ。
他の子はともかく、この「かいちゃちゃん」の本名が何だったのかがずっと謎だった。母が死ぬ前に教えてくれて「カズヒサ」だったことがわかった。呼び名とは妙なものだ。僕は「ぼやちゃん」と呼ばれていた。母親が「坊や」と言ったのが、名前と解釈されたらしい。「まあちゃん」のお父さんは、遠くで仕事をしているということだったが、実はコソ泥をしてしまって、刑務所にいたことも、60年経ってから知った。
ここでの、大きな事件は、13号台風だった。2015年にも常総市で洪水の被害があり、大きく報道されったが、結局死者はでなかった。当時は毎年、台風で死者が出るのが当たり前だった。1953年の台風13号は、死者393名行方不明85名という記録になっているから、熊本地震など昨今の自然災害の比ではない。
近くの与保呂川があふれて、家の周り一面も水が流れる状態になった。事態の深刻さを知らない僕は折り紙で舟を作って流したりしてご機嫌だった。ところが、水が玄関にも流れ込み、僕の下駄が浮き出した。このとき初めて恐怖を感じたのだろう。とたんに僕は泣き出してしまった。地についてるはずの下駄が浮きだしたことが恐怖の引き金になったのだ。プカプカ浮かぶ下駄を覚えている。消防団の人達が、僕を抱えて濁流を渡ってくれて、一段高い線路伝いに山際の神社まで避難した。
翌朝は晴れて、いい天気だったのだが、あたり一面は泥で埋まっていた。長靴を履いた僕も家に帰ろうとしたのだが、泥に長靴を取られて、すっぽり抜けた足で泥の中に踏み込んでしまった。これが、「しまった」と思った瞬間の最も古い記憶だ。その後も、「しまった」と思う度にこのときのことを思い出す。
これだけ鮮明な記憶が、確かに半世紀以上も昔のことであるとは、実に不思議な気がする。ときどき「あなたの一番古い記憶は何歳の時ですか?」と聞いてみるのだが、明確に答える人は少ない。
お正月の今昔 [若かった頃]
2017年の元旦を迎えた。今年は、連れ合いが腰痛に悩まされたままだし、子供たちも来ないので、手抜きで正月を過ごすことにした。初めて「おせち」を買ってみた。もちろん、何万円もする高級品が買えるわけではない。食べる人数も少ないのだからと、一番安そうなものを申し込んだのだが、それでも1万円だった。
ところが、年末に届いた包みを開いて驚いた。ハム、焼き豚、エビチリ、フカヒレスープ、野菜の煮物等々、単なるオードブルに過ぎないことになる。連れ合いは腰痛に鞭打って、今年も急きょおせちを作り出した。お煮しめ、ごまめ、なます、黒豆、きんとん、だてまき、かまぼこ、かずのこ、かしらいも。こういったものを漆のお重に詰めると色合いも美しい。雑煮をくって正月の気分を味わうことができた。
どうも世の中の「おせち」は変わってきているようだ。いや、お正月そのものが変わってきてしまっている。街にも松飾を見かけないし、お店も平常どおり営業している。一年に唯一度の元日という風景は失われている。
僕が子供のころ、正月は確実に日常ではなかった。門松は商店などに限られていたが、どの家にもしめ飾りがあった。家族団らんの日だから、すべての店は閉まっていた。これは1980年ころまで続いたと思う。1970年当時でも、正月なしで実験する学生は食堂が閉まっていることで往生した。
正月は家々で違ったものになる。我が家の元旦のお雑煮は、京風で頭芋のはいった白みそだった。それぞれの名前を書いた袋にはいった祝箸をつかう。全員で「明けましておめでとうございます」と唱えてから食べ始める。我が家には初詣などという宗教心はなかったので、出かけず、百人一首、カルタ取りなどをしてすごした。日ごろ忙しそうにしている母も、ちょっと余所行きの着物を着て仲間に加わる。わずかなお年玉がポチ袋に入って渡され、中を覗いてほくそ笑んだものだ。届いた年賀状の品評も楽しみだった。達筆な筆書きや版画など凝ったものが多かった。印刷はつまらない。お昼はおせちと、砂糖醤油をつけた焼餅だった。
2日になると、お雑煮は、ゆず三ツ葉を入れた澄まし汁に焼餅をいれたものになる。町は動き始め、「初荷」と旗を立ててトラックが国道を走った。行きかう車には「お飾り」がついていたし、時折、父の職場の人たちが年始回りにおとずれる。年始回りといった風習はもうないだろう。元旦は少し遠慮するのだが2日になると友達を誘う。ぼくらは、凧揚げに行ったり、コマ回しをして遊んだ。なぜかこういった遊びは正月にするものだと決まっていた。お昼には、焼餅に黄な粉を付けた「あべかわ」を食べた。
書初めをしたのは3日だったと思う。毎年必ずやることになっていた。家族全員が順次筆を執り、作品の出来不出来よりも、姿勢とかにうるさかった。「おうす」というのも我が家の慣例だった。座敷に正座させられ、茶筅で抹茶を掻き立てて母がお茶をいれる。にがいお茶を飲んでからでないと甘い羊羹のようなお菓子が食べられない。「けっこうでした」とご挨拶もしなければならない。
正月の三が日というのは、明らかにに特別な日だった。四日は仕事始めなのだが、街には振袖姿が目立った。若い女性社員は振袖を着て出社する。そんな格好だから仕事はしないで挨拶だけだ。当時は「時給」などという働き方はなかった。全ての人が正社員だからこそできたことだ。当時から正月営業したほうが儲かっただろうが、人々は金もうけよりも、特別な日を楽しむことを優先した。それは、一種の余裕だったかもしれない。正月が失われているというより、余裕が失われているというのが正しい。
ところが、年末に届いた包みを開いて驚いた。ハム、焼き豚、エビチリ、フカヒレスープ、野菜の煮物等々、単なるオードブルに過ぎないことになる。連れ合いは腰痛に鞭打って、今年も急きょおせちを作り出した。お煮しめ、ごまめ、なます、黒豆、きんとん、だてまき、かまぼこ、かずのこ、かしらいも。こういったものを漆のお重に詰めると色合いも美しい。雑煮をくって正月の気分を味わうことができた。
どうも世の中の「おせち」は変わってきているようだ。いや、お正月そのものが変わってきてしまっている。街にも松飾を見かけないし、お店も平常どおり営業している。一年に唯一度の元日という風景は失われている。
僕が子供のころ、正月は確実に日常ではなかった。門松は商店などに限られていたが、どの家にもしめ飾りがあった。家族団らんの日だから、すべての店は閉まっていた。これは1980年ころまで続いたと思う。1970年当時でも、正月なしで実験する学生は食堂が閉まっていることで往生した。
正月は家々で違ったものになる。我が家の元旦のお雑煮は、京風で頭芋のはいった白みそだった。それぞれの名前を書いた袋にはいった祝箸をつかう。全員で「明けましておめでとうございます」と唱えてから食べ始める。我が家には初詣などという宗教心はなかったので、出かけず、百人一首、カルタ取りなどをしてすごした。日ごろ忙しそうにしている母も、ちょっと余所行きの着物を着て仲間に加わる。わずかなお年玉がポチ袋に入って渡され、中を覗いてほくそ笑んだものだ。届いた年賀状の品評も楽しみだった。達筆な筆書きや版画など凝ったものが多かった。印刷はつまらない。お昼はおせちと、砂糖醤油をつけた焼餅だった。
2日になると、お雑煮は、ゆず三ツ葉を入れた澄まし汁に焼餅をいれたものになる。町は動き始め、「初荷」と旗を立ててトラックが国道を走った。行きかう車には「お飾り」がついていたし、時折、父の職場の人たちが年始回りにおとずれる。年始回りといった風習はもうないだろう。元旦は少し遠慮するのだが2日になると友達を誘う。ぼくらは、凧揚げに行ったり、コマ回しをして遊んだ。なぜかこういった遊びは正月にするものだと決まっていた。お昼には、焼餅に黄な粉を付けた「あべかわ」を食べた。
書初めをしたのは3日だったと思う。毎年必ずやることになっていた。家族全員が順次筆を執り、作品の出来不出来よりも、姿勢とかにうるさかった。「おうす」というのも我が家の慣例だった。座敷に正座させられ、茶筅で抹茶を掻き立てて母がお茶をいれる。にがいお茶を飲んでからでないと甘い羊羹のようなお菓子が食べられない。「けっこうでした」とご挨拶もしなければならない。
正月の三が日というのは、明らかにに特別な日だった。四日は仕事始めなのだが、街には振袖姿が目立った。若い女性社員は振袖を着て出社する。そんな格好だから仕事はしないで挨拶だけだ。当時は「時給」などという働き方はなかった。全ての人が正社員だからこそできたことだ。当時から正月営業したほうが儲かっただろうが、人々は金もうけよりも、特別な日を楽しむことを優先した。それは、一種の余裕だったかもしれない。正月が失われているというより、余裕が失われているというのが正しい。
ふるさとの空 [若かった頃]
お正月の間、晴れた日が多かった。やはり表日本だ。しかし、7日になって曇り空が現れた。これが僕にとっての冬らしい空だ。僕の育った山陰地方の冬と言えば、毎日がどんよりとした天気で、一月には何回か雪が降り、日陰には必ずザラメ雪の塊が残っていた。長靴をはいて、防空頭巾をかぶって遊びに出る。防空頭巾というのは、いまでは防災頭巾と言っているものだがもっと綿が分厚くて暖かいものだった。防空頭巾という呼び方は戦争中のものだが、戦後も同じ呼び方が続いていた。
冬は寒かったと思うが、子供たちは寒さをものともせず外で遊んだ。雪玉に泥を浸ませて強くした「きんかん」をぶつけ合って固さを競う。雪のへばりついて斜面を見つけて、竹を曲げたスキーやソリで遊ぶ。タコを作ってとばすこともやった。「子供は風の子、大人は火の子」と囃して寒がりを蔑んだものだ。
外遊びでかじかんだ手を温める家の中の暖房は、堀炬燵と火鉢だ。炬燵の燃料には練炭が使われていた。それが最新式で、多くの家では炭とか豆炭が使われていた。火鉢は木炭で、灰をかぶせて火力を調節する。寒いからと火鉢にまたがってお尻をあぶったりすると怒られた。火鉢には五徳があり、餅網をのせて餅を焼く。これだけで暖房が十分なわけはなく、家の中でも厚着だった。60年代になると、石油ストーブが入り、炬燵も電気式になっていった。
学校の暖房は石炭ストーブだ、だるま型のストーブと煙突が教室にあり、毎朝、当番がストーブに火をつける。新聞紙から木っ端そして石炭を入れる。良く燃えれば、鉄製のストーブの壁が真っ赤になるくらい高温になる。休み時間にはストーブの周りに子供たちは集まるのだが、自然に、ガキ大将のような奴が前を占める。女の子や弱弱しい連中は遠慮せざるを得ない。石炭を教室に運ぶのも当番の仕事だったが、なかなか重いものだった。
山に囲まれ、山の上には、冬のどんよりとした空がある。「山のあなたの空遠く、幸い住むと人の言う」といったカールブッセの詩が、ぴったりと当てはまる情景だ。だれもが未来を山のかなたに置いていた。田舎には大学も工場もないから、多くの子供たちはやがて山のかなたに出ていく事になるのは必然だったのである。
僕は高校の途中で転校して、この街を出てしまったのだが、同窓会には呼んでもらっている。多くの友達が東京や大阪に出てきてしまっており、町に残っているのは少ない。あいかわらず、曇り空の中にあり、徐々に寂れている町だ。ほとんどの人にとって、仕事ができる場所ではないから、帰るわけには行かないことになっている。都会に留まる決意を込めた犀星の思いとは異なるが、まさに「ふるさとは遠きにありて思ふもの」である。
あえてUターンして町に戻っている友達からの年賀状は、つまらない普通の年賀状ではあったが、僕には格別な趣があった。しかし、ここ何年かで相次いで他界してしまったから、それも途絶えた。あの元気な少年たちが、この世にいなくなったのである。僕がまだ命を永らえている事すら不思議な気がする。
ふるさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて異土の乞食となるとても
帰るところにあるまじや
ひとり都のゆふぐれに
ふるさとおもひ涙ぐむ
そのこころもて
遠きみやこにかへらばや
遠きみやこにかへらばや
冬は寒かったと思うが、子供たちは寒さをものともせず外で遊んだ。雪玉に泥を浸ませて強くした「きんかん」をぶつけ合って固さを競う。雪のへばりついて斜面を見つけて、竹を曲げたスキーやソリで遊ぶ。タコを作ってとばすこともやった。「子供は風の子、大人は火の子」と囃して寒がりを蔑んだものだ。
外遊びでかじかんだ手を温める家の中の暖房は、堀炬燵と火鉢だ。炬燵の燃料には練炭が使われていた。それが最新式で、多くの家では炭とか豆炭が使われていた。火鉢は木炭で、灰をかぶせて火力を調節する。寒いからと火鉢にまたがってお尻をあぶったりすると怒られた。火鉢には五徳があり、餅網をのせて餅を焼く。これだけで暖房が十分なわけはなく、家の中でも厚着だった。60年代になると、石油ストーブが入り、炬燵も電気式になっていった。
学校の暖房は石炭ストーブだ、だるま型のストーブと煙突が教室にあり、毎朝、当番がストーブに火をつける。新聞紙から木っ端そして石炭を入れる。良く燃えれば、鉄製のストーブの壁が真っ赤になるくらい高温になる。休み時間にはストーブの周りに子供たちは集まるのだが、自然に、ガキ大将のような奴が前を占める。女の子や弱弱しい連中は遠慮せざるを得ない。石炭を教室に運ぶのも当番の仕事だったが、なかなか重いものだった。
山に囲まれ、山の上には、冬のどんよりとした空がある。「山のあなたの空遠く、幸い住むと人の言う」といったカールブッセの詩が、ぴったりと当てはまる情景だ。だれもが未来を山のかなたに置いていた。田舎には大学も工場もないから、多くの子供たちはやがて山のかなたに出ていく事になるのは必然だったのである。
僕は高校の途中で転校して、この街を出てしまったのだが、同窓会には呼んでもらっている。多くの友達が東京や大阪に出てきてしまっており、町に残っているのは少ない。あいかわらず、曇り空の中にあり、徐々に寂れている町だ。ほとんどの人にとって、仕事ができる場所ではないから、帰るわけには行かないことになっている。都会に留まる決意を込めた犀星の思いとは異なるが、まさに「ふるさとは遠きにありて思ふもの」である。
あえてUターンして町に戻っている友達からの年賀状は、つまらない普通の年賀状ではあったが、僕には格別な趣があった。しかし、ここ何年かで相次いで他界してしまったから、それも途絶えた。あの元気な少年たちが、この世にいなくなったのである。僕がまだ命を永らえている事すら不思議な気がする。
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて異土の乞食となるとても
帰るところにあるまじや
ひとり都のゆふぐれに
ふるさとおもひ涙ぐむ
そのこころもて
遠きみやこにかへらばや
遠きみやこにかへらばや
ルージュの伝言 [若かった頃]
「ルージュの伝言」は荒井由実による1975年の作品だから相当古い歌だ。1989年に全く映画の内容とは関係ないのに、宮崎駿の趣味で「魔女の宅急便」に現れた。そのために、いまや誰でも知っている有名な歌になっている。この曲を初めて聞いた時の事を思い出す。特別に好きな歌というわけでもないのだが、思い出がある。
誰でも若いころは音楽に魅かれる。僕も大学に入ったころから音楽を聴くことが多くなった。当時の音楽はフォークソングだ。それまでの歌謡曲・民謡とは明らかに違う。世界を視野に入れ、その変革も目指している。If I had a hammer とか、We shall overcome が僕の気分にぴったり合った。だれもがギターを弾いてフォークソングを口にする時代だったのだ。
その後、フォークソングには日本的な歪曲が加わって行く。1970年以降の歌は、かつてのおおらかさを失い。自分の内面に閉じこもって行く(例えば井上陽水「傘がない」)とか、個人的な日常(例えば、遠藤賢治「カレーライス」)に終始するようになっていた。いわゆる4畳半フォークの時代だ「神田川」みたいな歌ばかりになった。
僕は、単純な学問的情熱だけで大学に入った。就職だとか将来の生活だとかは、これっぽっちも考えていない未熟者だったのである。当時の理学系の学生は大体そんなものだ。しかし、学問というのは夢見ていたほど甘くない。たちまち壁に突き当たってしまった。一方で、社会に目を向ければ変革の情熱を燃やすことも出来る時代だった。We shall overcome も、道いっぱいに広がって御堂筋を占拠して歌うものだった。ところが学生運動も、全共闘以来、内ゲバ暴力の時代になり、おおらかさを失ってしまった。
周りは壁だらけ、どう生きたら良いかを模索する日々になってしまった。せまい考えの中で堂々巡りをしていた。そういう人が多かったのかもしれない。歌は時代の反映である。
そんな時、岡林信康の「申し訳ないが気分がいい」に出会った。涼しい風が吹けば気持ちがいい。美しいものを見れば気分がいい。こういった当たり前のことを見落としていたという内容のものだ。僕らの時代の人以外に、気分がいいことに対して、申訳ないという感覚が理解できるだろうか。僕がとらわれていた屁理屈を超えた世界があることに気づいた。
岡林が糸口だったのだが、それに続いて決定的な追い打ちをかけたのが「ルージュの伝言」なのである。今までに聞いたことのないような、音の飛びを持った曲で、テンポも速い。歌の内容が、想像もつかないような別世界と感じられた。その頃、風呂場はあっても、壁が大きな鏡になっているバスルームといったものはなかった。むしろ庶民は銭湯に行くのが普通だった。バスルームの鏡に口紅で伝言を書くなどというのは仰天のほかない。
世の中には別の考えで、別の生活をしている人々がいる。「あの人のママ」とは義母、姑のことだ。なんという表現だろう。結婚もしている年齢なのにまったく、屈託がない。亭主が女の子に優しくしたことに焼餅をやいている。それをあの人のママに言いつけて叱ってもらうことが解決の道だと歌う。あり得ないのだが、自信を持ったリズムでゆるぎなくせまってくる。脱帽である。
人にはいろんな生き方がある。全ての人がアインシュタインやエンリコ・フェルミを目指さなくてもいいのだ。僕の世界は、あまりにも狭いということに気づかされた。それが「ルージュの伝言」なのである。それまで考えたこともなかった生活とか恋愛、結婚といった人並みのことにも目が向くようになった。連れ合いと出会ったのは、その頃なのだが、ま、この話はやめておこう。歌の受け止め方は人さまざま、ただこの歌を「この先を考えるとおそろしい、不倫発覚の歌」などという誤った受け取りだけは勘弁してほしい。
誰でも若いころは音楽に魅かれる。僕も大学に入ったころから音楽を聴くことが多くなった。当時の音楽はフォークソングだ。それまでの歌謡曲・民謡とは明らかに違う。世界を視野に入れ、その変革も目指している。If I had a hammer とか、We shall overcome が僕の気分にぴったり合った。だれもがギターを弾いてフォークソングを口にする時代だったのだ。
その後、フォークソングには日本的な歪曲が加わって行く。1970年以降の歌は、かつてのおおらかさを失い。自分の内面に閉じこもって行く(例えば井上陽水「傘がない」)とか、個人的な日常(例えば、遠藤賢治「カレーライス」)に終始するようになっていた。いわゆる4畳半フォークの時代だ「神田川」みたいな歌ばかりになった。
僕は、単純な学問的情熱だけで大学に入った。就職だとか将来の生活だとかは、これっぽっちも考えていない未熟者だったのである。当時の理学系の学生は大体そんなものだ。しかし、学問というのは夢見ていたほど甘くない。たちまち壁に突き当たってしまった。一方で、社会に目を向ければ変革の情熱を燃やすことも出来る時代だった。We shall overcome も、道いっぱいに広がって御堂筋を占拠して歌うものだった。ところが学生運動も、全共闘以来、内ゲバ暴力の時代になり、おおらかさを失ってしまった。
周りは壁だらけ、どう生きたら良いかを模索する日々になってしまった。せまい考えの中で堂々巡りをしていた。そういう人が多かったのかもしれない。歌は時代の反映である。
そんな時、岡林信康の「申し訳ないが気分がいい」に出会った。涼しい風が吹けば気持ちがいい。美しいものを見れば気分がいい。こういった当たり前のことを見落としていたという内容のものだ。僕らの時代の人以外に、気分がいいことに対して、申訳ないという感覚が理解できるだろうか。僕がとらわれていた屁理屈を超えた世界があることに気づいた。
岡林が糸口だったのだが、それに続いて決定的な追い打ちをかけたのが「ルージュの伝言」なのである。今までに聞いたことのないような、音の飛びを持った曲で、テンポも速い。歌の内容が、想像もつかないような別世界と感じられた。その頃、風呂場はあっても、壁が大きな鏡になっているバスルームといったものはなかった。むしろ庶民は銭湯に行くのが普通だった。バスルームの鏡に口紅で伝言を書くなどというのは仰天のほかない。
世の中には別の考えで、別の生活をしている人々がいる。「あの人のママ」とは義母、姑のことだ。なんという表現だろう。結婚もしている年齢なのにまったく、屈託がない。亭主が女の子に優しくしたことに焼餅をやいている。それをあの人のママに言いつけて叱ってもらうことが解決の道だと歌う。あり得ないのだが、自信を持ったリズムでゆるぎなくせまってくる。脱帽である。
人にはいろんな生き方がある。全ての人がアインシュタインやエンリコ・フェルミを目指さなくてもいいのだ。僕の世界は、あまりにも狭いということに気づかされた。それが「ルージュの伝言」なのである。それまで考えたこともなかった生活とか恋愛、結婚といった人並みのことにも目が向くようになった。連れ合いと出会ったのは、その頃なのだが、ま、この話はやめておこう。歌の受け止め方は人さまざま、ただこの歌を「この先を考えるとおそろしい、不倫発覚の歌」などという誤った受け取りだけは勘弁してほしい。
間質性肺炎で亡くなった旧友を悼む [若かった頃]
僕と同病の友人が亡くなったことを知った。フェースブックに自作の戒名がアップされて、エイプリルフールのいたずらかと思ったら、前日になくなっていた。死期を知り、あらかじめ公開日を指定しておいたらしい。
彼との30年来の付き合いは僕がアメリカにいた時に始まる。シカゴにも日本人は多く住んでいたが、大部分は北西の高級住宅街に住んでいて、そこには日本語学校もあった。僕は勤務の関係でかなり遠い西の郊外に住まざるを得なかったのだが、この地域には日本人があまりいない。子供たちの教育が問題で、日本語をあきらめてしまう人も多かった。そんな中でもシカゴまで通学バスを走らせることを組織した人たちがいた。
彼は熱心にバス運行を支えている父母の一人だった。毎週土曜日にバス停に集まり、子供たちを送り出したあとで、いろんなことを話し合って仲良くなった。「Get Nips out. Keep Ameria clean」などと落書きされたり、人種差別事件もあった。当時の在米日本人には面白い人物が多かったのだが、中でも彼の強烈な個性は光っていた。僕はいつも彼の話に引き込まれた。
1970年当時、外国に行くというのは勇気のいることだった。僕のようにいずれ日本に帰るあてがあれば気楽なのだが、職も決まっていない場合、相当な決心がいったと思う。それでも、アメリカに渡る人はいた。しかし、大抵は挫折して語学研修に終わる。彼のように大学院で化学を専攻して、博士の学位まで取るような人は少なく、並大抵の努力ではなかったはずだ。何事にも熱中するのが彼の性格であり、情熱を持って初志を貫徹する人だったのだ。
彼がイリノイ州に来たのは大手食品会社クラフトの研究員になったからだ。そこで彼はマイコンに出会った。70年代の末、ワンチップCPUが現れ、新しいコンピュータの時代が始まったころだ。化学とは全く分野違いなのだが、小さなチップに埋め込まれたコンピュータの魅力に取りつかれ、安定した研究生活と高給を放り投げて独学でコンピュータの世界に飛び込んだのだ。零細企業に転職して、「マッドプラネット」とかのアーケードゲームの開発に没頭した。なんという思い切りの良さだろう。
やがて彼は独立して、ソフトウエア会社を立ち上げた。マイクロソフトなどの下請けでいくつものソフトウエアの分担をこなしたりしていたが、もちろんそんな生業を続けるつもりはなかった。彼の会社の主力製品として映像用のDATテープを使った記憶装置を開発した。テープなのにまるでディスクのように働く。ディスク容量がMBの時代に、GBの容量をもった記憶装置の普及に意気込んでいた。
彼の家の地下室には世界本社(world headquarter)の看板を掲げていたが、従業員は彼一人だ。ベンチャービジネスが皆アップルのような成功を収めるわけではない。いや、むしろほとんどの会社が数年で消えていく。生き残ることさえ稀な世界だ。半導体メモリーの発展は目覚ましく、今では100ギガバイトのメモリーも普通になっているくらいだから、彼の大容量記憶装置は残念ながら普及する前に時代遅れになってしまった。
しかし、その付属として作ったファイルコピーのソフトが生き残った。いろんなソフトをインストールする時に、多くのファイルをコピーしなくてはならないのだが、これを効率よく行うために彼のソフトが今も各社で使われている。彼の会社は、今に至るまで20年以上も続いた。自分一人でプログラムを作り、それで家族を養っていけた人が何人いるだろうか。
僕は数年で日本に帰ったのだが、その後もイリノイを訪れるたびに、彼にあったりしていた。大変なお世話になったこともある。僕がパスポートを紛失してしまい、途方に暮れたことがある。領事館で帰国のための認証をしてもらおうと思ったら、保証人が要ると言う。あの時は彼に保証人になってもらってやっと帰国することができた。僕が酸素を抱えるようになってからも、POCを使ってアメリカには行った。その時、間質性肺炎については、いろいろと彼に説明をした。
3年前、彼から「俺も間質性肺炎になったらしい」と連絡があった。skypeで話をしたのだが、どうも十分な検査ができていないように思えた。自営業みたいなものだから、保険が十分カバーしていない。治療しても無駄だなどと言われていた。それで、彼は日本に帰国して治療を受ける気になったらしい。彼は東京の名門高校の出身で、同級生には著名な医者も多い。
帰国しての治療で彼は見違えるように元気を取り戻した。我が家にも来てくれて久しぶりの再会を楽しんだ。いつもながらの彼の元気のいい話ぶりにこちらが励まされた。何事にも熱中するという彼の性格は素晴らしい。子供たちがバイオリンを習い始めた時には、彼自身も練習を始め、家族でカルテットを組むと言うことまでやった。帰国してからは碁を始め、これも一年で初段を取った。
彼のフェースブックに、酸素量が増えたことが書いてあったのはつい一か月前のことだ、肺高血圧症が出て入院したのだが、2週間前に退院して、一段落したと思っていた。まさかと疑ったが、奥さんから電話があって確定した。元気であっても、間質性肺炎の最後は急接近してくるものらしい。
精一杯生きた一人の人間として彼の生きざまには学ぶところが多い。実に立派だと思う。冥福を祈るばかりだ。
彼との30年来の付き合いは僕がアメリカにいた時に始まる。シカゴにも日本人は多く住んでいたが、大部分は北西の高級住宅街に住んでいて、そこには日本語学校もあった。僕は勤務の関係でかなり遠い西の郊外に住まざるを得なかったのだが、この地域には日本人があまりいない。子供たちの教育が問題で、日本語をあきらめてしまう人も多かった。そんな中でもシカゴまで通学バスを走らせることを組織した人たちがいた。
彼は熱心にバス運行を支えている父母の一人だった。毎週土曜日にバス停に集まり、子供たちを送り出したあとで、いろんなことを話し合って仲良くなった。「Get Nips out. Keep Ameria clean」などと落書きされたり、人種差別事件もあった。当時の在米日本人には面白い人物が多かったのだが、中でも彼の強烈な個性は光っていた。僕はいつも彼の話に引き込まれた。
1970年当時、外国に行くというのは勇気のいることだった。僕のようにいずれ日本に帰るあてがあれば気楽なのだが、職も決まっていない場合、相当な決心がいったと思う。それでも、アメリカに渡る人はいた。しかし、大抵は挫折して語学研修に終わる。彼のように大学院で化学を専攻して、博士の学位まで取るような人は少なく、並大抵の努力ではなかったはずだ。何事にも熱中するのが彼の性格であり、情熱を持って初志を貫徹する人だったのだ。
彼がイリノイ州に来たのは大手食品会社クラフトの研究員になったからだ。そこで彼はマイコンに出会った。70年代の末、ワンチップCPUが現れ、新しいコンピュータの時代が始まったころだ。化学とは全く分野違いなのだが、小さなチップに埋め込まれたコンピュータの魅力に取りつかれ、安定した研究生活と高給を放り投げて独学でコンピュータの世界に飛び込んだのだ。零細企業に転職して、「マッドプラネット」とかのアーケードゲームの開発に没頭した。なんという思い切りの良さだろう。
やがて彼は独立して、ソフトウエア会社を立ち上げた。マイクロソフトなどの下請けでいくつものソフトウエアの分担をこなしたりしていたが、もちろんそんな生業を続けるつもりはなかった。彼の会社の主力製品として映像用のDATテープを使った記憶装置を開発した。テープなのにまるでディスクのように働く。ディスク容量がMBの時代に、GBの容量をもった記憶装置の普及に意気込んでいた。
彼の家の地下室には世界本社(world headquarter)の看板を掲げていたが、従業員は彼一人だ。ベンチャービジネスが皆アップルのような成功を収めるわけではない。いや、むしろほとんどの会社が数年で消えていく。生き残ることさえ稀な世界だ。半導体メモリーの発展は目覚ましく、今では100ギガバイトのメモリーも普通になっているくらいだから、彼の大容量記憶装置は残念ながら普及する前に時代遅れになってしまった。
しかし、その付属として作ったファイルコピーのソフトが生き残った。いろんなソフトをインストールする時に、多くのファイルをコピーしなくてはならないのだが、これを効率よく行うために彼のソフトが今も各社で使われている。彼の会社は、今に至るまで20年以上も続いた。自分一人でプログラムを作り、それで家族を養っていけた人が何人いるだろうか。
僕は数年で日本に帰ったのだが、その後もイリノイを訪れるたびに、彼にあったりしていた。大変なお世話になったこともある。僕がパスポートを紛失してしまい、途方に暮れたことがある。領事館で帰国のための認証をしてもらおうと思ったら、保証人が要ると言う。あの時は彼に保証人になってもらってやっと帰国することができた。僕が酸素を抱えるようになってからも、POCを使ってアメリカには行った。その時、間質性肺炎については、いろいろと彼に説明をした。
3年前、彼から「俺も間質性肺炎になったらしい」と連絡があった。skypeで話をしたのだが、どうも十分な検査ができていないように思えた。自営業みたいなものだから、保険が十分カバーしていない。治療しても無駄だなどと言われていた。それで、彼は日本に帰国して治療を受ける気になったらしい。彼は東京の名門高校の出身で、同級生には著名な医者も多い。
帰国しての治療で彼は見違えるように元気を取り戻した。我が家にも来てくれて久しぶりの再会を楽しんだ。いつもながらの彼の元気のいい話ぶりにこちらが励まされた。何事にも熱中するという彼の性格は素晴らしい。子供たちがバイオリンを習い始めた時には、彼自身も練習を始め、家族でカルテットを組むと言うことまでやった。帰国してからは碁を始め、これも一年で初段を取った。
彼のフェースブックに、酸素量が増えたことが書いてあったのはつい一か月前のことだ、肺高血圧症が出て入院したのだが、2週間前に退院して、一段落したと思っていた。まさかと疑ったが、奥さんから電話があって確定した。元気であっても、間質性肺炎の最後は急接近してくるものらしい。
精一杯生きた一人の人間として彼の生きざまには学ぶところが多い。実に立派だと思う。冥福を祈るばかりだ。
思い出す海へのあこがれ夏休み [若かった頃]
孫の誕生日には本をプレゼントすることにしている。早いものでお姉ちゃんは6年生、12歳になる。思うに12歳というのは子供として一番充実する時だ。この後は大人としての一歩が始まってしまうし、楽しいばかりの人生ではなくなる。僕は12歳の時にどんな本を読んだだろうか?やっぱり冒険物語だろう。
15少年漂流記、ロビンソンクルーソー、スイスのロビンソン、宝島、黒い海賊、ガリバー旅行記。うっ。航海物ばかりだ。海辺に住んでいた関係もあって、実は海へのあこがれで僕の頭は占められてしまっていたのである。そうでなくともあの時代、遠くへ行くとは船に乗ることだった。今でさえ外国は「海外」と言うくらいだ。
せっせと模型の船を作りながら、いつか航海に出る夢を膨らませていた。しかし、毎日学校がある日々の生活は、こうした冒険物語の世界とはかけ離れており、あまりにも現実から遠かった。だが夏休みとなれば学校はない。だから夏休みの物語となれば急に現実味が出てくるように感じられた。
子供だけで帆船をあやつるといった素晴らしい夏休みを物語にしてくれていたのが、アーサー・ランサムだ。僕はこのシリーズの物語をわくわくしながら読んだのだが、どういうわけか、あまり知られていない。岩波書店が38巻もの全集にしているのに不思議なことだ。
ハリーポッターは全部読んでしまったというお姉ちゃんに今年プレゼントするのは「ツバメ号とアマゾン号」がいい。おばあちゃんは冷ややかな目で見ている。「女の子よ。海の冒険なんておバカな男の子とは違うのよ。」そんなことはない。「ツバメ号とアマゾン号」では女の子が活躍するのだ。
僕と同じように海にあこがれているわけではないだろうが、お姉ちゃんには結構冒険心があると見ている。6年生の夏休みはとても大切なのだが、お姉ちゃんの場合は充実しており、それなりの冒険があったと思う。
UCLAのチアリーダーたちが指導するスポーツキャンプに行って少し英語も覚えてきた。新学期が始まり、修学旅行ということで鎌倉に行き、居合わせた外国人に話しかけて一緒に写真をとってきたから、いい度胸だ。同行の友達は驚いてしまい、運動会での活躍と共に武勇伝化しているそうだ。
せっせと本も読んで、読書感想文のコンクールでは入選になった。仲間を募って雪合戦に参加した。近くにある冷凍機の会社が雪を提供してくれて、真夏に雪合戦をやると言うのが恒例のローカル行事なのだ。友達に声をかけてまわり、11人のチームを集められたのは素晴らしい。丸めた新聞紙の玉で練習して優勝ということになった。NHK首都圏ニュースにインタビューされて嬉しそうな顔を見せていた。
海にあこがれただけの夏休みでさえ心に残る。思い切り遊べた夏休みはやはり人生の宝物だろう。
15少年漂流記、ロビンソンクルーソー、スイスのロビンソン、宝島、黒い海賊、ガリバー旅行記。うっ。航海物ばかりだ。海辺に住んでいた関係もあって、実は海へのあこがれで僕の頭は占められてしまっていたのである。そうでなくともあの時代、遠くへ行くとは船に乗ることだった。今でさえ外国は「海外」と言うくらいだ。
せっせと模型の船を作りながら、いつか航海に出る夢を膨らませていた。しかし、毎日学校がある日々の生活は、こうした冒険物語の世界とはかけ離れており、あまりにも現実から遠かった。だが夏休みとなれば学校はない。だから夏休みの物語となれば急に現実味が出てくるように感じられた。
子供だけで帆船をあやつるといった素晴らしい夏休みを物語にしてくれていたのが、アーサー・ランサムだ。僕はこのシリーズの物語をわくわくしながら読んだのだが、どういうわけか、あまり知られていない。岩波書店が38巻もの全集にしているのに不思議なことだ。
ハリーポッターは全部読んでしまったというお姉ちゃんに今年プレゼントするのは「ツバメ号とアマゾン号」がいい。おばあちゃんは冷ややかな目で見ている。「女の子よ。海の冒険なんておバカな男の子とは違うのよ。」そんなことはない。「ツバメ号とアマゾン号」では女の子が活躍するのだ。
僕と同じように海にあこがれているわけではないだろうが、お姉ちゃんには結構冒険心があると見ている。6年生の夏休みはとても大切なのだが、お姉ちゃんの場合は充実しており、それなりの冒険があったと思う。
UCLAのチアリーダーたちが指導するスポーツキャンプに行って少し英語も覚えてきた。新学期が始まり、修学旅行ということで鎌倉に行き、居合わせた外国人に話しかけて一緒に写真をとってきたから、いい度胸だ。同行の友達は驚いてしまい、運動会での活躍と共に武勇伝化しているそうだ。
せっせと本も読んで、読書感想文のコンクールでは入選になった。仲間を募って雪合戦に参加した。近くにある冷凍機の会社が雪を提供してくれて、真夏に雪合戦をやると言うのが恒例のローカル行事なのだ。友達に声をかけてまわり、11人のチームを集められたのは素晴らしい。丸めた新聞紙の玉で練習して優勝ということになった。NHK首都圏ニュースにインタビューされて嬉しそうな顔を見せていた。
海にあこがれただけの夏休みでさえ心に残る。思い切り遊べた夏休みはやはり人生の宝物だろう。
さいなら三角またきて四角 [若かった頃]
家の傍に小高い丘があった。丘よりも急峻なところがあったから山である。雑木が茂り、曲がりくねった山道がいくつもあった。ここが僕らの遊び場だ。腰に刀を差して連れ立って歩いた。もちろん、そんなおもちゃを買ってもらえるものでもなく、自分で木を削って刀の形にしあげたものだ。時折、「曲者!」と叫んで、手裏剣ならぬ木片を投げて見る。
「なあ、今黒い影が走っただろ」
必ず調子をあわせる奴がでてくる。「そこにも!」と叫んで手裏剣を投げる。
「うむ、仕損じたか」「素早い奴だ」
「あれは伊賀者だ」
「僕たち甲賀だもんね」
やがて道はちょっとした広場に出る。そこは一面ススキ野原になっていた。遊びは鬼ごっこに切り替わる。身の丈ほどものススキが生い茂っているから、身を隠すことが出来る。かがんで素早く動けば、鬼が来たころには、もうそこにはいない。神出鬼没の忍者を演ずることができるのだ。
遊んでいると時間が経つのが早い。やがて、ススキの原に夕日が射すようになる。空にはトンビが悠然と舞い、あんな風に飛べたらなあと、しばらく見上げていたりする。みんなの顔が赤く染まった頃、決まってカラスの鳴き声が聞こえる。もう家に帰らなくてはいけない。「カラスが鳴くからかーえろ」は本当だ。
また連れ立って山を下りる。名残惜しいが友達とも別れの挨拶をしなくてはならない。
さいなら三角また来て四角
四角は豆腐 豆腐は白い
白いはウサギ ウサギは跳ねる
跳ねるは蛙 蛙は青い
青いは柳 柳は揺れる
揺れるは幽霊 幽霊は消える
消えるは電気 電気は光る
光はオヤジの禿げ頭
結構長いのだが、この歌を友達の家の前に来るたびに繰り返す。家に帰った頃には日が暮れてあたりは薄暗くなっている。いつものように「いつまで遊んでいるの」と怒られそうだ。これは一種のざれ歌だが、誰に教わったと言うことはない。ただみんな歌っていた。連れ合いに尋ねたら九州天草島でもこの歌を歌っていたと言う。僕がいた若狭湾とはこんなにも離れているのに、どうやって伝わったのだろうか。実に不思議である。
「なあ、今黒い影が走っただろ」
必ず調子をあわせる奴がでてくる。「そこにも!」と叫んで手裏剣を投げる。
「うむ、仕損じたか」「素早い奴だ」
「あれは伊賀者だ」
「僕たち甲賀だもんね」
やがて道はちょっとした広場に出る。そこは一面ススキ野原になっていた。遊びは鬼ごっこに切り替わる。身の丈ほどものススキが生い茂っているから、身を隠すことが出来る。かがんで素早く動けば、鬼が来たころには、もうそこにはいない。神出鬼没の忍者を演ずることができるのだ。
遊んでいると時間が経つのが早い。やがて、ススキの原に夕日が射すようになる。空にはトンビが悠然と舞い、あんな風に飛べたらなあと、しばらく見上げていたりする。みんなの顔が赤く染まった頃、決まってカラスの鳴き声が聞こえる。もう家に帰らなくてはいけない。「カラスが鳴くからかーえろ」は本当だ。
また連れ立って山を下りる。名残惜しいが友達とも別れの挨拶をしなくてはならない。
さいなら三角また来て四角
四角は豆腐 豆腐は白い
白いはウサギ ウサギは跳ねる
跳ねるは蛙 蛙は青い
青いは柳 柳は揺れる
揺れるは幽霊 幽霊は消える
消えるは電気 電気は光る
光はオヤジの禿げ頭
結構長いのだが、この歌を友達の家の前に来るたびに繰り返す。家に帰った頃には日が暮れてあたりは薄暗くなっている。いつものように「いつまで遊んでいるの」と怒られそうだ。これは一種のざれ歌だが、誰に教わったと言うことはない。ただみんな歌っていた。連れ合いに尋ねたら九州天草島でもこの歌を歌っていたと言う。僕がいた若狭湾とはこんなにも離れているのに、どうやって伝わったのだろうか。実に不思議である。